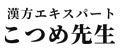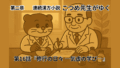「こつめ君、今月の数字、まだ目標に届いてないぞ」
営業所の会議室。
グラフと数字を並べた資料を前に、上司の声が響いた。
「抗生物質は横ばいや。もっと処方を取れるように働きかけんと」
言葉は理解できても、胸の奥は冷えていくばかりだった。
患者の声は聞こえない。
どれだけ“喜んでもらえた”としても、それは評価されない。
その日の帰り道。
ふと、仕事で立ち寄った町の商店街に、古びた看板が目に入った。
「漢方薬 ○○堂」
小さな引き戸を開けると、薬草の香りがふわりと漂った。
棚には茶色い瓶や和紙に包まれた薬草。
奥のカウンターには、白衣姿の店主がゆったりと腰を下ろしていた。
「いらっしゃい。今日はどうされました?」
ちょうど中年の女性客が座っていて、体調の相談をしている最中だった。
店主はメモを取りながら、頷き、時には笑い、時には静かに耳を傾けていた。
「最近、疲れやすくて…」
「そうですか。それなら、冷えもあるみたいですし――陽虚気味やな」
店主はそう言って、いくつかの薬草を取り出した。
「体を温めて、気を補う漢方を合わせましょう」
30分ほど、丁寧に話を聴いたあとで調合を始める。
その横顔は、どこか懐かしい。
――おばあちゃんが棚を開けながら語ってくれた姿と重なった。
女性客が帰ったあと、店主がこちらを見た。
「……君は薬屋さんか?」
「ええ、まあ。今は製薬会社で営業をしています」
「なるほど」店主は顎に手を当てて微笑んだ。
「それにしては、さっきから目が真剣やったな」
ぼくは思わず聞いてしまった。
「……先生、何を処方されたんですか?」
店主は少し驚いたように眉を上げた。
「ほう、君は漢方に詳しいのか?」
「いえ、詳しいってほどではありません。
ただ、祖母がよく“人は体質によって薬が違うんや”って話してまして」
店主は静かにうなずいた。
「なるほど。ええ話やな。やっぱり漢方は“人そのもの”を診て処方するもんや」
しばらく沈黙が流れ、やがて店主がゆっくりと言った。
「こつめ君。薬ってのは数字のためにあるんやない。
数字は会社に報告するためのもんや。
けど薬は、患者さんの“ありがとう”に応えるためにあるんや。
人の声にこそ効くんやで」
その言葉が、胸の奥を射抜いた。
まさに、自分が探していた答えだった。
店を出ると、夜風が頬を打った。
でも心は、不思議と軽かった。
数字のグラフではなく、人の声の中で働きたい――。
その思いが、初めて迷いなく形を取った。
「……転職しよう」
小さな声が、確かに自分の中から聞こえた。
[つづく]
▶︎ 第16話『修行の日々』
(こつめ青年、漢方薬店で新たな一歩を踏み出す)