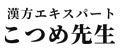朝の京都。
冬の名残を残す冷たい風が、商店街ののれんを揺らしていた。
「今日は私、町内の会合で出るからな」
師匠は白衣の袖を整えながら言った。
「こつめ君、今日は一日、店を任せる」
「えっ……ぼ、僕ひとりで?」
「大丈夫や。薬は棚にある。
あとは“人”を見て決めることや」
穏やかな眼差しとともに微笑むと、師匠は静かに店を出ていった。
午前中は常連の患者が数人。
こつめは慎重に調剤し、何とか無事に対応していた。
だが昼過ぎ、一人の老婦人が店に入ってきた。
背を少し丸め、両手をこすり合わせながら言う。
「先生、体が冷えて仕方ないんです。
靴下を何枚重ねても、指先の感覚がなくて……」
こつめは脈を取りながら考えた。
脈は細くて弱く、押すとすぐに消えてしまう。
冷えが芯まで入り込んでいる――陽虚の脈だった。
「体を温めるお薬を考えますね」
そう言いながら棚を見上げた。
目に入ったのは、真武湯と人参湯。
“冷えには真武湯や”と頭の中で繰り返すが、
女性の声が、ふと耳に残った。
「お風呂に入ると少しマシになるんです。でもすぐ冷えるんです」
――それは、単なる冷えではない。
体を温めても、その“火”を保てない。
陽気そのものが弱っている。
こつめは一包の箱を取り出した。
「……人参湯にしましょう」
数日後、その女性がまた来た。
「先生、あの薬を飲んでから、
朝、起きたときの冷えが少しマシになったんです」
こつめの胸に、静かな達成感が広がった。
“温める”とは、外から火を足すことではない。
中の火を燃やす力――つまり“気”を取り戻すこと。
ある日、師匠が帳簿を見ながら言った。
「こつめ君、留守のときどうやった?」
「はい……。少し怖かったです。でも、
患者さんが“楽になった”と笑ってくれました」
師匠は穏やかにうなずいた。
「陽虚の人は、体の火が弱るだけやない。
心の火も小さくなっとる。
――火を足すよりも、燃やす力を取り戻さなあかん。
それを見極めるのが、漢方家や」
外は、春を告げる雨が静かに降り始めていた。
こつめは灯りの落ちた店内で、
調剤台の上に置かれた小さな湯のみを手に取る。
白い湯気がゆっくりと立ちのぼり、
彼の心の奥に、小さな火をともした。
[つづく]
▶︎ 第19話『黒豹の眼差し ―瘀血の学び―』
(心の奥に傷を抱えた女性、柊さんとの出会い)