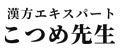「こつめ、ちょっと来てくれるか?」
そう言われて、ぼくは薬棚の整理を途中でやめた。
いつもの声。いつもの調子。でも、何かが違った。
縁側に、おばあちゃんが座っていた。
畳に映る影が、いつもより細くて、頼りない。
「こつめ。あんた、よう手ぇ動かすようになったなぁ。
最初は、棚の“さ”の字も知らんかったのにな」
「…そんなん、おばあちゃんが毎回“棚の奥の物語”聞かせてくれるからやん」
ぼくは笑って言ったけど、
その瞬間、おばあちゃんの目がふっと遠くなった。
「ええか、こつめ。
この“漢方のまど”は、“誰かの苦しみの窓”でもある。
そこを一緒に、そーっと開けるのが、漢方家の仕事や。
“ぐいっ”て開けたらアカンで」
「……」
「つらい時こそ、そばに立ってることが薬になる。
そんな“漢方家”に、なってくれたら、うれしいな」
その夜、母から伝えられた。
「おばあちゃん、入院することになったんよ」
ぼくは、返事ができなかった。
胸の中で、何かが小さく、でも確かに音を立てていた。
そして、数日後――
白衣が似合う人やったな、って思う。
薬草の名前よりも、あの手の温もりを、もっと覚えとけばよかった。
最後の棚の引き出しを開けると、
そこには、古びた包み紙と、文字が一枚。
「こつめへ
“さよなら”は、やさしい言葉や。
それは“また、会える”って意味もあるからな」
ぼくは声に出して、もう一度読んだ。
「さよなら、おばあちゃん」
でも、その“さよなら”は、
きっと“始まり”やったんやと思う。
[つづく]
▶︎ 第11話『バイクで走る風の中で』
(青年期編、ついに始動――)