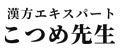大学を卒業して、ぼくはある製薬メーカーに就職した。
配属先は“病院まわり”を担当する営業、いわゆるMR。
新しい肩書きにまだ慣れないまま、研修を終えて初めて現場に出る日が来た。
「本日から病院まわりに出てもらうからな」
先輩が分厚い資料を手渡してくれる。
抗生物質や解熱剤など、新薬の主力製品が並ぶリストの端に、ひとつだけ見慣れた名前があった。
補中益気湯。
思わず口に出してしまった。
「これも扱ってるんですね」
先輩は苦笑した。
「まあ正直、漢方はおまけや。処方数も少ないし、興味持つ先生は限られてるからな」
最初に訪れたのは、総合病院の内科外来だった。
白衣の医師はモニターに向かい、電子カルテを打ち込みながら次の患者を呼び出している。
慌ただしい空気にのまれそうになりながらも、ぼくは勇気を出して切り出した。
「先生、先ほど補中益気湯を処方されてましたが……」
医師は顔を上げず、短く言った。
「ごめん、時間ない。資料だけ置いてって」
かばんの中で準備してきた言葉は、そこで途切れた。
深々と頭を下げ、机の端に資料を置いて診察室を後にする。
廊下のベンチには、診察を待つ患者たちが座っていた。
疲れた顔、咳き込む人、不安げに時計を見つめる人。
その中の誰かが、さっき補中益気湯を手にしたのだろう。
けれど、ぼくの立場からは、その患者に言葉を届けることはできない。
病院を出ると、先輩が肩を軽く叩いて笑った。
「気にすんな。最初はみんなそうや」
ぼくは黙ってうなずいた。
先生には話せなかった。患者さんの声も聞けなかった。
それでも――あの棚で見た薬草の名前が、今も処方箋に生きている。
それだけが、少しだけ胸を温めていた。
[つづく]
▶︎ 第14話『数字の向こうに』
(営業成績と現場の違いに悩む日々)