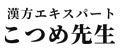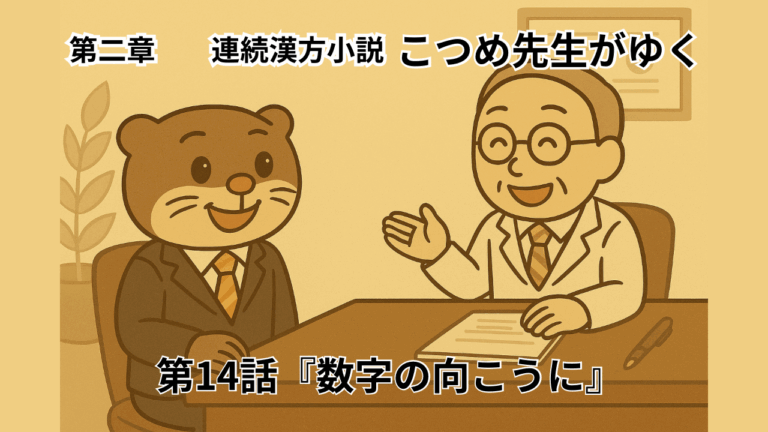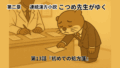営業所に戻ると、机の上には報告書の山が待っていた。
今日訪問した病院名、担当医、面談時間、そして――処方数。
パソコンの画面には棒グラフが並び、赤い線が「目標」を示している。
「ここを越えんと、評価はされへんぞ」
先輩がコーヒーを片手に言う。
「患者の顔を思い浮かべても意味はない。数字がすべてや」
言葉は冷たかったが、事実でもあった。
MRは医師に薬を説明し、処方につなげる。
その成果は数字でしか測れない。
翌日、ぼくは一人で町のクリニックを訪ねた。
待合室には、風邪気味の親子や、検診帰りの高齢者が腰掛けている。
診察室に通されると、初老の医師がにこやかに出迎えてくれた。
「おう君か、若いのにご苦労さんやな。
この前は六君子湯をちょっと出したんや。患者さんが“胃が楽になった”て喜んでな」
先生は話好きらしく、こちらが切り出す前に近況を語り始めた。
そして、カルテを閉じながら何気なく口にした。
「そういや、前に出した補中益気湯の患者さんもな、
“体力戻ってきた”て喜んでたんや。
ああいうのは、数字には表れんけど、効いてる証拠やな」
胸の奥が熱くなった。
昨日の病院では、忙しい医師に遮られ、
「漢方はおまけや」と先輩に言われたばかりだった。
けれど、今この瞬間、確かに一人の患者に届いていた。
補中益気湯は、誰かの生活を変えていた。
営業所に戻ると、上司に呼び止められた。
「こつめ、抗生物質の数字が伸びてへんぞ。
もっとアピールして数字を積まんと」
画面には数字だけが並んでいた。
そこに“体力が戻って喜んだ患者”の顔は、当然どこにもない。
夜、資料を整理しながら、ぼくは思った。
確かに数字は大事や。
けど、薬の向こうにいるのは人や。
その人の変化は、グラフにも報告書にも載らない。
おばあちゃんの言葉がふっと蘇る。
「つらい時こそ、そばに立ってることが薬になる」
営業マンとしては不器用なのかもしれない。
でも、心のどこかで分かっていた。
数字の向こうにこそ、本当の答えがある――と。
[つづく]
▶︎ 第15話『転職の決意』
(こつめ青年、漢方薬店の扉を叩く)