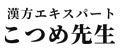春の光が差し込む京都の町並み。
その一角にある古びた漢方薬局の引き戸を、こつめ青年は両手で押した。
「今日からよろしくお願いします」
深々と頭を下げる。
先日偶然立ち寄ったこの店に、正式に勤めることになったのだ。
奥から現れたのは、落ち着いた風貌の先生が、穏やかな眼差しでこちらを見つめる姿だった。
「まあ、すぐに大したことはできん。まずは人をよう見なさい」
静かで柔らかな声だったが、不思議と胸の奥に響いた。
こうして、こつめ青年の京都での修行の日々が始まった。
⸻
最初に相談に来たのは、四十代の女性。
椅子に腰かけるなり、「毎日疲れて疲れて、何をしても元気が出ません」とため息をついた。
声には張りがなく、話の途中で何度も息継ぎをしている。
師匠がこつめに小声で問いかける。
「どう見る?」
「……体が冷えているんでしょうか」
「違う。よく聞け。この人は冷えてるんやなくて、力そのものが不足してる」
⸻
師匠は患者の手首にそっと触れ、しばらく目を閉じた。
「……脈が全体に大きいように見えるやろ。でもな、力がない。
締まりもなく散ってしもてる。まるで風船のような脈や」
こつめはごくりと唾を飲み込んだ。
「それが――気虚、ですか?」
師匠はうなずき、柔らかな声で答えた。
「そうや。これが補中益気湯を必要とする“虚の脈”や」
⸻
棚から薬草を取り出しながら、師匠は続ける。
「疲れやすい、声に力がない、食欲が落ちやすい。こういう人には“気”を補わなあかん」
袋に混ぜられたのは、黄耆・人参・白朮――。
「これは補中益気湯。元気を底から支える処方や」
⸻
こつめは分量を秤にかける役を任された。
だが手が震え、針が大きく揺れる。
「あっ……」
「こら。焦るな。薬はグラムで効くんやない。
心を落ち着けて、人の声に合わせて秤を動かすんや」
師匠の声に背筋を正す。
呼吸を整え、慎重に針を合わせる。
ようやく一包が仕上がった。
⸻
患者は薬を受け取りながら、少し笑顔を見せた。
「なんだか、元気が出そうな気がします」
その笑顔に、こつめの胸が熱くなった。
数字でもグラフでもない――たったひとつの「声」。
それが薬の力を照らしている。
⸻
夜、店を閉めたあと。
師匠が静かに語った。
「こつめ君。気虚の患者には“補う”ことが大事や。
でもな、薬草だけやない。患者さんが“生きたい”と思える気持ちを支えるのも、漢方家の役目や」
その言葉が、深く胸に刻まれた。
⸻
[つづく]
▶︎ 第17話『窓辺の京都から ―陰虚の学び―』
(潤いを失った患者との出会い)