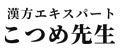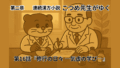初夏の風が、窓辺の暖簾をやさしく揺らしていた。
こつめ青年は、すり鉢を片手に薬草をすり合わせながら、
その音のリズムで自分の呼吸を整えていた。
師匠に教わった「気虚」の学びから、まだ日も浅い。
それでも、患者の表情や声の調子に少しずつ敏感になっている自分を感じていた。
その日、来店したのは三十代の女性だった。
細い腕、頬は赤くほてり、目の下にうっすらと影。
話し方は静かだが、ところどころで息が続かない。
「夜、寝汗をかくんです。それに喉がいつも乾いて……」
師匠が頷きながら、こつめに目で合図を送る。
「どう見る?」
こつめは考え込んだ。
「……体の中に熱がこもっているのかもしれません」
師匠は静かに笑った。
「そう見えるやろ。でも違う。これは“火”やのうて、“潤い”が足りてへんのや」
師匠は脈を取り、しばらく沈黙した。
「細くて、軽い。まるで枯れ枝の上を風が渡るような脈やな。――陰虚や」
そう言って、机の上に並べた薬草を一つひとつ指さした。
「この人には冷ますんやなくて、潤すんや。体の中の泉を掘り起こすようにな」
こつめはその言葉を反芻しながら、
麦門冬・天門冬・甘草をそっと秤にかけた。
患者が帰ったあと、師匠は窓辺に腰を下ろし、
差し込む午後の光を見つめながら言った。
「こつめ君。人は“乾く”と、心も尖ってくる。
体が潤えば、心もやわらぐんや。
薬は体に効くようでいて、ほんまは心に届くんやで」
その言葉に、こつめは小さくうなずいた。
その日の夕暮れ。
西日が窓に映る瓶の中で、麦門冬の淡い影が揺れていた。
こつめはその光景を、しばらくの間、静かに見つめていた。
“潤い”とは、水ではなく、生きようとする力の余白。
そんな言葉が、胸の奥にふっと浮かんだ。
[つづく]
▶︎ 第18話『ひとりで立つ日 ―陽虚の学び―』
(初めて店を任されるこつめ青年、温める力を試される)