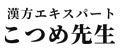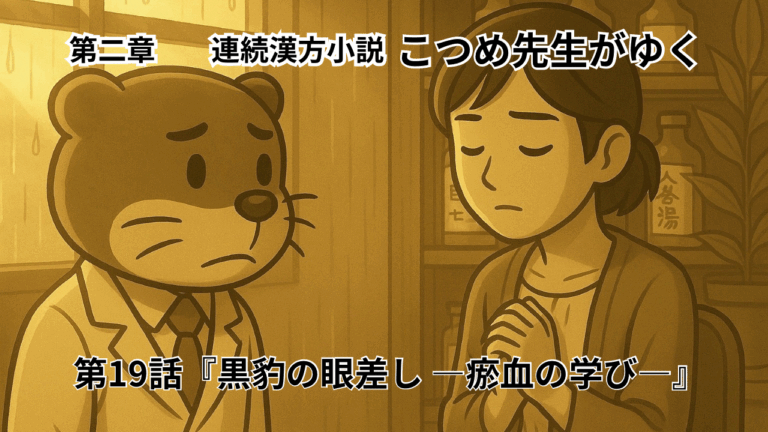京都の午後。
雨上がりの光が、薬棚の瓶に柔らかく反射していた。
こつめは調剤台を拭きながら、
湯気のように漂う生薬の香りに、師匠の声を思い出していた。
――人をよう見なさい。体だけやのうて、心もや。
引き戸の鈴が、かすかに鳴った。
「……こんにちは」
静かな声。
顔を上げると、黒髪を短くまとめた女性が立っていた。
生成りのワンピースに、薄い灰色のカーディガン。
柔らかいのに、どこか張りつめた空気を纏っている。
「最近、体が重くて……胸がつかえるような感じがして、夜も眠れないんです。
月のものも乱れていて、時々、息苦しくなることもあります」
師匠はうなずき、静かに言った。
「では、舌を見せてもらえますか」
午後の日差しが差し込む。
彼女がそっと舌を出すと、
淡い光の中に、わずかに紫を帯びた赤が浮かび上がった。
その表面には、細かな暗い点がいくつも散っている。
師匠の目が細められる。
「……血の流れが滞っとるな。
体の奥で、澱(おり)のように血が沈んどる。
無理に流すんやなく、自分で動き出せるように手を貸すんや」
そう言って師匠は、棚から小瓶を取り出した。
ラベルには、細い文字で「田七人参」。
粉末を掌にすくい、光にかざす。
淡い茶色が、雨上がりの陽にきらりと光った。
「これは、血の道を開く薬や。
滞りを少しずつ、やわらかくしていく」
こつめは、その説明を聞きながら、
女性――柊の横顔を見つめていた。
透けるような肌の奥に、言葉にならない疲れが見えた。
まるで、長いあいだ光に触れていなかった花のように。
会計を済ませたあと、柊は紙袋を抱きしめるようにして言った。
「……いっそ、楽になれたらいいのに」
師匠は何も言わず、ただその背を見送った。
こつめは胸の奥で、何かが静かに軋むのを感じた。
店内には、田七人参の香りと、
雨の名残を含んだ風が混ざっていた。
瓶に映る光がゆらぎ、
柊の姿が、静かに溶けていくように見えた。
こつめは目を閉じた。
その瞼の裏に――
黒豹のように深く、美しい光を宿した瞳が、
いつまでも静かに揺れていた。
[つづく]
▶︎ 第20話『別れの処方箋 ―師弟の約束―』
(突然の事故、そして託されたもの)