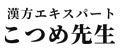京都の朝は、少し肌寒かった。
店に差し込む光は淡く、雨上がりの匂いがまだ微かに残っている。
こつめは調剤台の布をしぼりながら、
昨日の柊さんのことを思い返していた。
暗い紫を帯びた舌。
かすれた声。
「……いっそ、楽になれたらいいのに」
あの一言が、胸の奥のどこか深い場所に刺さったままだった。
その時、背後から声がした。
「……こつめ君、まだ気になっとるんやな」
師匠だった。
いつもと変わらぬ穏やかな眼差しなのに、
その優しさが返って余計に胸が締めつけられた。
「助けたいのに、助けられへんと感じる時もある。
でもな――その気持ちが、薬を選ぶ“心”を育てるんや」
こつめは静かに頷いた。
その瞬間、携帯が震えた。
画面を見ると、母の名前。
“守口市”の二文字が、胸に重くのしかかる。
「……もしもし?」
『こつめ……すぐ帰ってきてくれへん?
おばあちゃんの家のことで、大事な話があるねん……』
母の声はかすかに震えていた。
◆ 守口にて
久しぶりに歩く守口の道は、
相変わらずどこか優しくて、どこか寂しかった。
商店街はシャッターの数が増え、
子どもの頃に駆け回った場所は少し色あせて見えた。
角を曲がる。
そこに――
おばあちゃんの家兼・旧漢方店 があった。
でも、その前に見慣れぬスーツの男たちが立っていた。
「老朽化していますし、再開発区域です。
今なら高く買い取れますよ」
胸に、大手ドラッグチェーンのロゴ。
店を、おばあちゃんの思い出を、
いとも簡単に“値段”で測ってくる。
母はうつむき、
叔父は腕を組んだまま黙っている。
風が吹き、
古い家の木の匂いがこつめの鼻先をかすめた。
――あぁ、おばあちゃんの匂いや。
涙がこぼれそうになるのを奥歯でこらえた。
壊させたくない。
消させたくない。
ここは、おばあちゃんが最後まで守っていた場所や。
その思いが、胸の中で熱く膨らんでいく。
◆ 師匠へ
京都に戻ると、こつめは真っ先に師匠の元へ向かった。
事情を全部話した。
師匠は、ただ静かに聞いてくれた。
途中で遮らず、否定もせず、最後まで。
話し終えると、
店内の空気はしんと静まり返った。
しばらく考え込んだあと――
師匠は、こくりと頷いた。
「こつめ君。
あんた……その店、守りたいんやな?」
その一言で、
堰を切ったように涙があふれた。
「守りたい……です。
僕……逃げたくない。
おばあちゃんの店を……なくしたくないんです」
師匠は席を立ち、
こつめの肩に手を置いた。
それは、温かくて、少し震えていた。
「行きなさい」
短い言葉なのに、
胸の奥の深いところまで届いた。
「でも、師匠……僕、戻ってこられないかもしれません」
こつめは涙を拭うこともできず、
ただ震える声で言った。
師匠は、ふっと優しく笑った。
「こつめ君。
師匠のところに戻るとか戻らんとか、
そんなちっぽけな話やない」
師匠は棚の薬瓶にそっと触れながら、続けた。
「人はな、
“心が動いた場所”に、生涯戻るんや。
たとえ離れても、心は帰ってくる。
それが――
こつめ君への……処方箋や。」
涙がつっ、とこつめの頬を伝った。
「師匠……ありがとうございました……」
声にならない声だった。
師匠はゆっくりうなずき、
最後にひとことだけ言った。
「まだ終わりやない。
あんたの人生はこれからや。
わしはここで、いつでも見てるぞ。」
その瞬間、
こつめは深く、深く頭を下げた。
師匠の温かな視線が、背中にそっと触れた気がした。
◆ 別れの朝
店を出ると、
朝の光が少しだけ強くなっていた。
暖簾が揺れたたびに、
おばあちゃんの笑い声が聞こえるような気がした。
こつめは、守口へ向かう道を歩き始めた。
軽くはない。
でも確かに前へ向かう一歩。
師匠の教えと、おばあちゃんの思いと、
昨日の柊さんの“痛み”も胸に抱えたまま。
それら全部が――
こつめを押し出していた。
[つづく]
▶︎ 第三章スタート!
第21話『迷いの灯 ―成人期の幕開け―』
(おばあちゃんの店を守りながら現実にぶつかり、こつめの心の灯が揺れ始める)