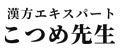「こつめ、ちょっとこっち来て手ぇ貸して。」
店の奥で、おばあちゃんが漢方棚の引き出しを一つずつ開けながら、何かを探していた。
「今日はな、昔のお客さんが久しぶりに来はるんよ。ちょっと特別な調合や。」
ここは、大阪の下町にある小さな薬店──
『漢方のまど』。
季節ごとの草花が飾られた店先には、今日もゆっくりとした空気が流れている。
こつめ少年は、その横で材料の準備を手伝いながら、いつもと違う薬の香りに鼻をくすぐられた。
「なぁ、おばあちゃん。」
「なんや?」
「“漢方家”って、なんなん?」
おばあちゃんは手を止めて、しばし考えるように宙を見つめたあと、ゆっくりと口を開いた。
「うちみたいな“漢方家”はな、
“治す”だけが仕事やないんや。」
「じゃあ、何するん?」
「“聴く”ことや。身体のことだけやない。
暮らしのこと、気持ちのこと、ぜんぶ聴いて、ようやく処方ができる。」
こつめは、しばらく黙って考えていた。
「それって……なんや、むずかしいな。」
「せや。でもな、“漢方のまど”っていう店の名前にも意味があんねんよ。」
「え? 窓って、どんな?」
「“こころに風が通る窓”って意味や。
うちに来た人が、話して、笑って、泣いて、
ちょっとでも軽うなって帰れたらええなって。」
そのとき、チリンと入り口の鐘が鳴った。
姿勢よく立ち上がり、深く一礼するおばあちゃんの背中を見て、
こつめは思った。
──なんや知らんけど、かっこええな。
その夜。こつめは一人、漢方棚の前に座っていた。
「“漢方家”って、かっこええ。
ボク、“漢方のまど”を継げるようになりたい。」
誰に向けるでもないその声は、
けれど、確かに未来へ伸びていた。
“志”という芽が、静かに育ちはじめた。
【つづく】
▶ 次回予告タイトル:
第10話『さよなら、おばあちゃん』
別れの朝、こつめ少年が手にした“志”というバトン。